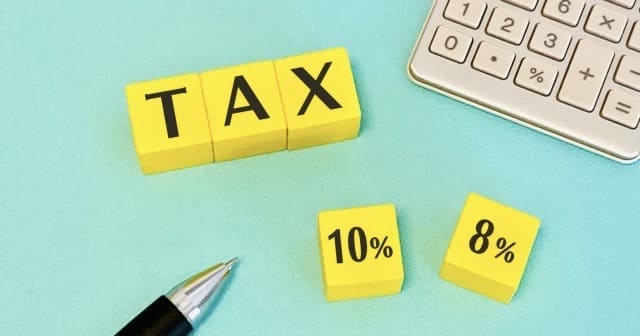ECサイト運営
ECサイトにおける離脱率とは?高いときの原因と改善策を解説!
ECサイトの運営において離脱率を確認することは重要ですが、離脱率についてよく理解していないという人も多いでしょう。本記事では、ECサイトにおける離脱率とは何か、計算方法や改善策まで詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
目次
ECサイトの離脱率とは?
Webマーケティングにおける離脱とは、ユーザーがサイト内にあるリンクから次のページへ遷移せずに、そのサイトを見るのをやめてしまうことを指します。ユーザーがサイトの閲覧をやめてしまうため、商品が売れる可能性はなくなります。離脱率が高いECサイトというのは、コンテンツや商品に魅力がなくユーザーから飽きられているとも言えるでしょう。
離脱率の計算方法
離脱率には、大きく分けて「サイト全体の離脱率」と「特定のページの離脱率」の2つがあります。サイト全体の離脱率は「サイト全体の訪問数÷サイト全体のPV数」、特定のページの離脱数は「そのページの離脱数÷そのページのPV数」の計算式で求められます。
たとえば、100人が特定のページを閲覧して、そのうち50人が次のページに遷移しなかった場合の離脱率は50%となります。運営側としては、少しでもユーザーの購買意欲を高めるために魅力あるコンテンツを提供して離脱率を低くするようなサイト運営が求められます。
離脱率をチェックする目的
離脱率をチェックする主な目的は、「サイト内のどのページに大きな問題があるか」を見極めるためです。ECサイトの目的は、基本的にはユーザーに商品を購入してもらって利益を得ることです。その目的のためには、サイト全体の構成やつながりはもちろん、個別ページの内容の充実も重要な要素となります。しかし、ただ漠然とサイト内をチェックしただけでは客観的な指標がないため、どの部分が悪いか分からない状態に陥りがちです。
そこで、特定のページの離脱率が客観的な指標の1つとして役立ちます。離脱率が高いページというのは、そこでユーザーの興味がなくなっているということなので、そのページを改善することで売り上げアップも見込めるでしょう。離脱率が高いページを定期的にチェックして原因を特定することで、迅速かつ効率的なサイト運営が可能になります。
直帰率との違いは?
離脱率とよく似た言葉に「直帰率」というものがあります。離脱率と直帰率はどちらも「ページを閲覧したユーザーがそれ以上見るのをやめた割合」という点では変わりません。ただし、離脱率が「サイトを訪れたユーザーが複数ページを閲覧後、最終的にどのページで閲覧をやめたかの割合」であるのに対して、直帰率は「最初に開いたページから1ページも遷移せずに閲覧をやめた割合」です。ECサイトの売り上げにとっては、どちらも低いほうが良いのは間違いありません。
直帰したユーザーはひとつもリンクを開いていないことから、ウインドウショッピングのような感覚でサイトを閲覧しているユーザーも多いです。それに対して、離脱率はそれなりに興味を持ってサイトを複数ページ閲覧してくれていたユーザーが去った割合を表しています。ライト層ではなく実際に売り上げにつながりそうな顧客を重要視するのであれば、離脱率のほうを気にしましょう。
離脱率の確認方法
離脱率は特定の条件を満たしていれば簡単に確認できます。その条件とは、「サイトにGoogleアナリティクスを導入しているかどうか」です。導入していれば、全体の離脱率はもちろんページ別の離脱率も簡単に確認できます。
サイト全体の離脱率を確認する場合は、まず管理画面を開いて左にあるメニューから「行動」を選択しましょう。次に「概要」を選択してサマリーを表示させるとグラフが表示されるはずです。そのグラフの上部にあるページビュー数を離脱率に変更すれば、折れ線グラフで離脱率が表示されるようになっています。
一方、個別ページの離脱率を表示させたい場合には、「行動」を選択したあとで「サイトコンテンツ」を開きます。その後、サイトコンテンツの下に表示される「すべてのページ」を選択すれば、離脱率を含めた各ページのデータが表示されるはずです。折れ線グラフに個別ページの離脱率を反映させたい場合には、サイト全体のときと同様にグラフ上部のプルダウンから「離脱率」を選択します。
離脱率で注意するページとポイント
離脱率は基本的に低ければ低いほど良いですが、高いからといって一概に改善するポイントであるとは言えません。なぜなら、ユーザーはさまざまな目的でECサイトを訪れているからです。最初から商品の購入までは考えておらず、ただチェックするだけの目的だったユーザーも一定数います。そのため、離脱率は運営が目標にする部分と近いページから重点的にチェックすることが重要です。ECサイトの場合では、売り上げに直結する「申し込みページ」が最も重視する項目だと言えるでしょう。次いで「カートページ」「商品詳細ページ」「トップページ」の順にチェックすると良いです。
商品の申し込みページの離脱率が高い場合には、「サイトや商品に対する不安を払拭できていない」「入力フォームが分かりにくかった」などの問題がある可能性があります。あと一歩で顧客を取り逃がしてしまわないように、重点的に改善方法を検討しましょう。
離脱率に問題がある場合の8つの原因と改善策
ECサイトの重要なページの離脱率が高い場合は、早急に対策を取らないといけません。しかし、原因はさまざまなので、適した対処をしないと効果的に離脱率を低下させることは難しいでしょう。そこでこの段落では、ECサイトの離脱率が高くなっているときに考えられる8つの原因と改善策について説明していきます。
ユーザーの求めていた情報がない
離脱率が高くなる原因として代表的なのは、開いたページにユーザーの求めている情報がないケースです。一般的に、ユーザーは自分の求めている情報を得るためにサイトを訪れています。検索サイトで表示された関連のあるサイトのうち、最も情報を得られそうなページを深読みするケースが多いです。内容が不十分であったり、ニーズにマッチしていなかったりする場合にはすぐに他のサイトへ興味が移ってしまいます。
ページの情報に原因があるかどうかを知る手段としては、滞在時間を参考にする方法があります。離脱率が高いページの滞在時間が他のページと比較して短い場合には、ユーザーが満足するような情報がなかったと考えられます。そのような場合は、検索サイトを経由してきたユーザーを囲い込めるように、ページタイトルと整合性が取れるようなコンテンツを展開していくように修正しましょう。
ページが見づらい・分かりづらい
ユーザーのニーズに合った情報が掲載されているにもかかわらず離脱率が高いページがある場合には、サイトの構成に問題がある可能性があります。ネットワーク環境の高速化が進み、時間に追われることの多くなった現代人は、一目見てすぐに情報を得られるサイトを好む傾向が強くなっています。「ランディングページが見づらく必要な情報に気づきにくい」「閲覧しにくくてストレスを感じさせてしまう」といったことが離脱の原因になりやすいです。
この場合の改善策としては、「商品購入につながるリンクボタンを大きくする」といった、CVポイントを意識したレイアウトに見直すと良いでしょう。また、スマホを使用してWebページの閲覧をするユーザーが増えている点も注意しておかなければいけません。スマホに対応していないWebページの場合、ユーザーが「文字が小さい」「画面拡大が煩わしい」といった不満を持つ可能性があります。サイトがスマホに対応していない場合は、早急に改善について検討しましょう。
入力フィールドが多い
ユーザーの多くは、商品の購入にあまり手間をかけたくないと考えています。そのため、商品の購入にあたって入力フィールドが多いと、敬遠されてしまうおそれがあります。例えば、「商品の購入前にアカウントを作成しなければならない」「入力する項目数が多い」といった事例です。商品購入までのプロセスが面倒だと離脱するユーザーも多くなり、リピーターになりにくくなるという点は注意しましょう。
入力フィールドが多いことが原因であるかどうかを突き止めるためには、商品申し込みページの離脱率をチェックしてみると良いです。商品申し込みフィールドの離脱率が高いということは、サイトの情報量やレイアウトには問題なく誘導できていると言えます。商品申し込みページの入力フィールドに不必要な項目はないか見直して、本当に必要なものだけを残すようにしましょう。不要な項目かどうかを判断できない場合には、大手ECサイトの入力フィールドを参考にしてみるのもひとつの方法です。
ページの表示が遅い
ページの表示速度が遅いと、離脱率が高くなりやすいです。インターネットを利用したことのある人なら、誰しもが一度は「サイトがなかなか表示されなくてイライラする」という経験をしたことがあるでしょう。せっかく効率的に情報を得ようとしてサイトを訪れたにもかかわらず、なかなかサイトが表示されないと待っている時間が無駄になってしまいます。無駄な時間を過ごすぐらいなら、他のサイトに移ってしまうというわけです。
ページの表示速度は、ユーザーの通信速度にもよりますが、解像度の高い写真や動画など容量の大きいものを多く掲載すると遅くなります。売り上げアップのためにきれいな画像や動画は必要かもしれませんが、ユーザーが待ちきれずに離脱してしまっては本末転倒です。バランスの取れたサイトに仕上げていくことが重要だと言えます。
Webページの表示速度を改善するために、「Google PageSpeed Insights」というツールを使用するのも一つの手です。ページの表示速度を測ってくれるだけでなく、高速化に必要な修正項目をリストアップしてくれるので、Webサイトの作成経験が少ない初心者でも比較的簡単に扱える点が魅力と言えます。
サイトの信頼度が低い
コンプライアンスや個人情報が重視されるようになった現代社会では、大手企業を中心に情報流出のためのさまざまな対策が施されています。しかし、対策を行っても不正アクセスやサーバー攻撃によって情報が流出するケースは少なくありません。ECサイトの商品購入に関する手続きでは、個人情報の入力が必須です。商品を届けるための住所や氏名、代金を支払うためのクレジットカードの番号など、ユーザーはかなり深い部分の個人情報を入力する必要があります。しかし、信頼できない店舗の入力フォームにそのような個人情報を入力してくれるでしょうか。
実際に、「商品を購入する際に信頼してクレジットカード情報を入力することができずに離脱する」というユーザーは一定数存在します。だからこそ、ユーザーからの信頼を高めるための対策をとらなくてはいけません。具体的には、世界的な送金手段として信頼されているPayPalのロゴや、セキュリティソフトとして有名なNortonのSECUREシールといったトラストマークを活用すると良いでしょう。
追加コストに抵抗がある
ユーザーは、「できるだけお得に良い商品を手に入れたい」と考えているものです。もしも、カートや商品の申し込みページにおける離脱率が高い場合、送料や手数料、消費税といった商品代金以外の追加料金によって離脱している可能性があります。改善策としては、可能な限り送料を最小限にして、手数料などの追加料金が発生する場合には、事前に告知しておくことが挙げられます。追加コストをあとになって突然ユーザーに知らせると、購入について再考してしまい離脱につながりやすいからです。
どうしても送料のコストを安くできない場合には、最初から商品代金に含めたうえで「送料無料」をアピールする方法も有効です。自店舗で行える場合は、ポイントを付与するなどの特典を付けてアピールする方法もあります。送料や手数料といった部分は、店舗側のアイデア次第でユーザー側の受け止め方が変わりやすいです。ユーザーの視点に立ったアピール方法を考えましょう。
返品についての記述がない
サイトのどこにも返品についての記述がない場合も、離脱率は高くなりやすいです。なぜなら、ECサイトはインターネット上で商品を購入するため、現物を確認できません。結果的に、実店舗で購入するよりも「商品が思っていたものと違っていた」というトラブルが起こりやすいからです。「何かあったときに返品が難しければそのサイトでは購入しない」と考えているユーザーも一定数います。
基本的には、返品ポリシーを明確に記載することでユーザーに安心感を与えることが重要です。中古品を扱っている場合などで返品を受け付けられないサイトもあるでしょうが、そのような場合でも「返品は受け付けない」と商品ページの目立つ場所に強調しておくと良いです。大切なのは返品を受け付けない理由であり、それが正当性を保っていればユーザーは納得して購入してくれるでしょう。
使いたい決済手段がない
利用者の希望する決済方法がない場合、離脱率は高くなります。ECサイトの利用者は、クレジットカード決済を利用する人が多いです。しかし、すべての利用者がクレジットカード決済を希望しているわけではありません。クレジットカード決済では、「商品が届いてから支払いたい」「支払いタイミングを自分で決めたい」といった利用者のニーズに応えることができず、離脱する可能性があります。
売上ランキング上位のECサイトでは、クレジットカード、コンビニ払い、代引き、その他キャッシュレス決済など、4つ以上の決済方法を導入している場合がほとんどです。そのため、利用者のニーズに応えるためにできるだけ多くの決済方法を導入しておくのが理想的だと考えられます。
離脱率改善は、購入直前の決済方法の最適化から始めよう
離脱率改善には、利用者にあった決済方法を導入することが有効です。ネットプロテクションズの調査によると、希望する決済手段がない場合には利用者の50%がそのネットショップで購入しない意思決定をしていることが分かりました。加えてネットショップでは、クレジットカード決済の次に後払い決済をしたいと考えている利用者が多いです。
後払い決済など、クレジットカード決済以外の決済手段を拡充することで、ユーザーの購入直前での離脱を防ぐ効果が期待できます。後払い決済サービスの「atone(アトネ)」は、業界で唯一値引きに使えるポイントが貯まり、電話番号とパスワードのみでスマホで簡単に決済可能なのでユーザーの申し込みページにおける離脱を防ぐのに貢献します。
離脱したユーザーにはカゴ落ちメールが有効
離脱した人の中には、在庫を確保するために「とりあえずカートに入れておこう」と行動を起こす人もいます。加えて、他のサイトと値段などを比較するという目的で商品をカートに入れる人もいます。一度は興味を持った商品であるため、カートに入れていることを思い出すと購入につながる可能性があります。
商品をカートに入れたことを忘れている人には、カートに商品が入ったままになっていることをメールで伝えてみましょう。この対策は「カゴ落ちメール」と呼ばれています。カゴ落ちメールが届くと、軽い気持ちで商品をカートに入れた利用者に対してのリマインド効果が期待できます。
▼「カゴ落ちメール」の文面や構成について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【例文付き】カゴ落ちメールとは?メール配信のポイントと文面を解説
離脱率を改善して購入数・成約数を向上させよう
ここまで、ECサイトの離脱率をチェックして改善する必要性や、離脱率が高い場合の原因と改善策について取り上げてきました。せっかく集客に成功しても、途中で離脱されてしまっては意味がありません。これまで離脱率を見ずにサイトを運営していた方は、すぐに離脱率改善に取り組むのが良いでしょう。
離脱率を改善するためには、ユーザーの動きを想定してミスマッチを減らしていくことが大切です。ユーザー目線でサイトの使い心地をチェックしてみましょう。
また、前述したatone(アトネ)の特徴や導入実績については、より詳しくご覧いただける資料をご用意しています。資料請求は無料で可能です。気になる方はぜひ資料をご確認ください。