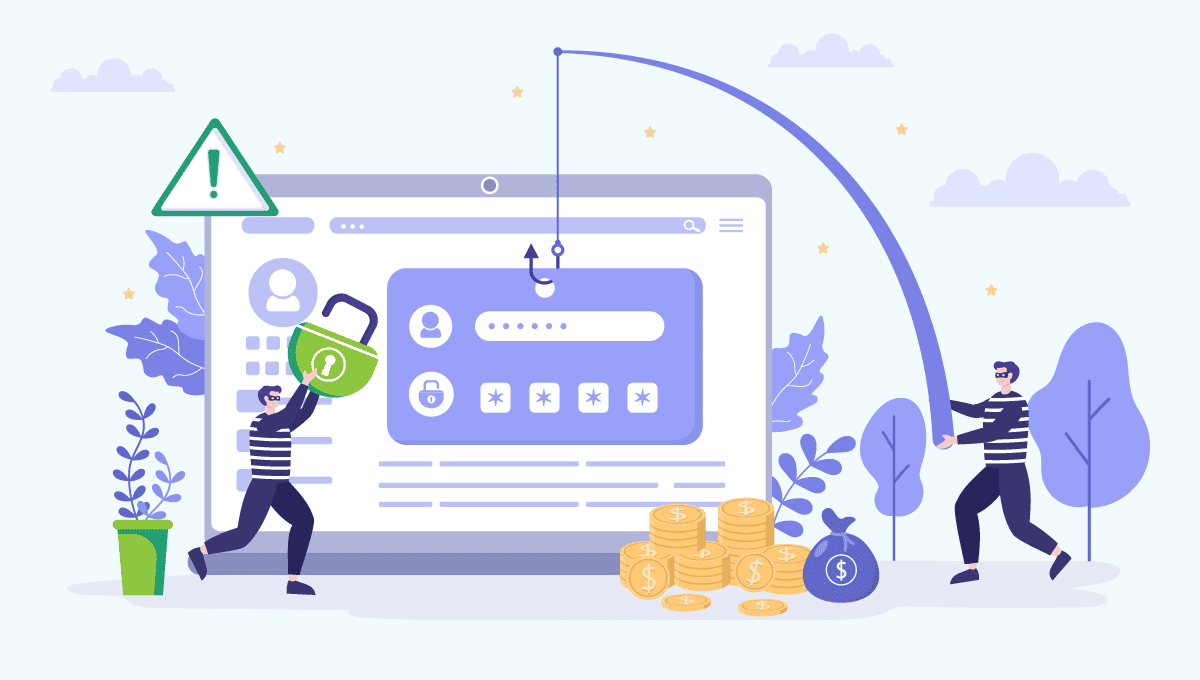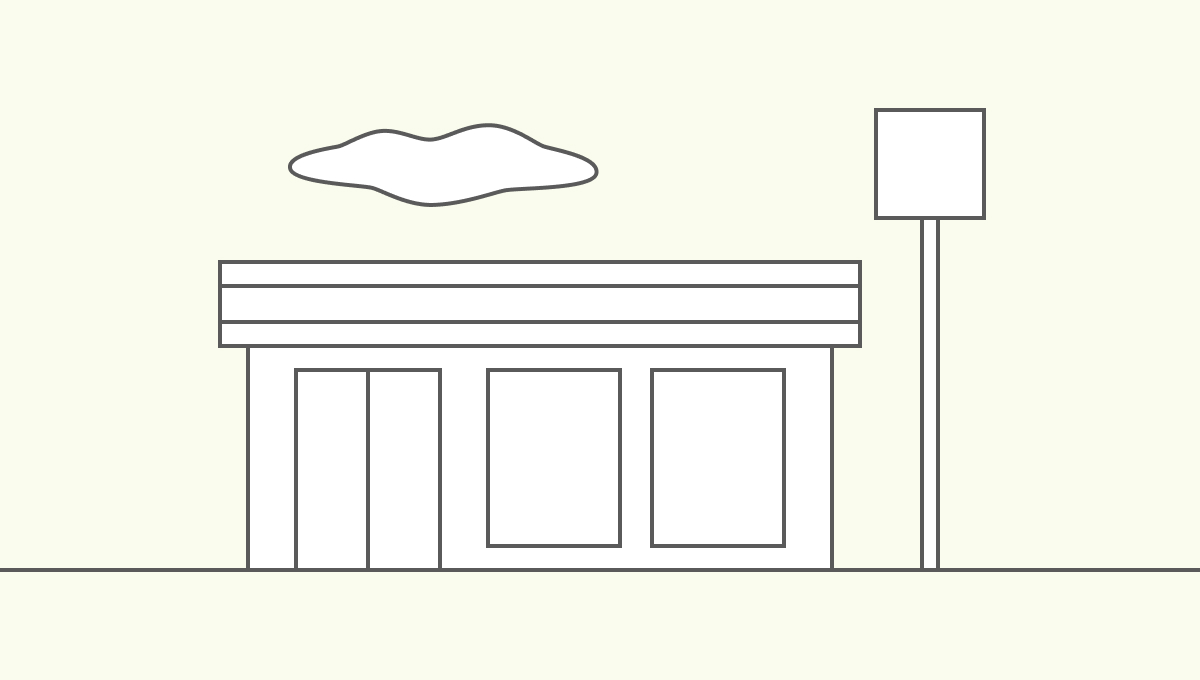決済
電子マネーは便利?電子マネーの種類と利用時のリスクについて解説
ECサイトはもちろんのこと、実店舗でも活用が広がっている電子マネー。2011年から2021年の10年間で、電子マネーの利用世帯は30.6%から58.0%に増加しました(※)。すでに半数以上の世帯が電子マネーを利用していることになります。
この記事では、電子マネーの仕組みや種類、利用者側・店舗運営者側から見た場合のメリット・デメリットについてわかりやすく解説します。電子マネー利用時のリスクにも触れていますので、電子マネーへの理解を深める上で役立ててください。
※出典:総務省統計局「家計消費状況調査年報(令和3年)結果の概況」
目次
電子マネーとは
電子マネーとは、データ化してやり取りできるお金のことを指します。現金を扱うことなく、電子的なやり取りのみで決済が完了する点が大きな特徴です。
データ化されているとはいえ、電子マネー1円分の価値は現金の1円と変わりません。さまざまな店舗やサービスが発行する独自のポイントとは異なり、あくまでも「お金」として扱われます。
電子マネーの仕組み
電子マネーの基本的な仕組みは、利用者(消費者)と店舗の間に「電子マネー発行者」が介在することで成り立っています。
1. 利用者が電子マネー発行者に現金を提供する
2. 電子マネーが発行される
3. 電子マネーを利用して買い物をする
4. 店舗は発行者から電子マネーを受け取る
上記の通り、電子マネーで使った金額が発行者から店舗へ後日支払われているのです。
電子マネーの種類
電子マネーと一口に言っても、実はいろいろな種類があります。電子マネーを大きく分けると、「クレジットカード」「交通系電子マネー」「流通系電子マネー」「スマートフォン決済・QRコード系電子マネー」の4種類です。それぞれの特徴や使い方について解説します。
クレジットカード
カード型の電子マネーで、クレジットカードに付帯する機能として提供されています。実店舗ではカードに埋め込まれたICチップを端末に差し込んで読み込ませるか、もしくはタッチ決済を活用するのが一般的です。
ECサイトでは、クレジットカード番号や有効期限、名義人、セキュリティコードなどを入力することで決済できます。利用した金額は後日まとめて請求され、銀行引き落とし等で支払う仕組みです。
交通系電子マネー
鉄道会社が発行する電子マネーです。公共交通機関を利用する際に使われているほか、対応している店舗でも利用できます。
カード型の電子マネーのほか、スマートフォンの専用アプリで利用することも可能です。利用するには事前にチャージ(入金)しておく必要があります。鉄道の各駅に設置された端末から現金でチャージするほか、クレジットカードによるチャージにも対応しています。
流通系電子マネー
スーパーマーケットやコンビニなどの流通系企業が発行している電子マネーです。発行元の店舗で利用できるほか、他社の店舗等での利用にも対応しているものが多く見られます。
発行元の系列店舗で利用するとポイントが貯まりやすいなど、特典を設けているケースが少なくありません。電子マネーによりますが、カードに加えスマートフォンアプリで利用できるものもあります。基本的には事前にチャージして利用する先払い型ですが、流通系企業が発行するクレジットカードと紐付けることでチャージが可能なものも見られます。
スマートフォン決済・QRコード系電子マネー
スマートフォンアプリを使用して支払うタイプの電子マネーです。銀行口座やクレジットカードを紐付けておくことで、入金が可能となります。
支払い時にはスマートフォンに表示されたQRコードやバーコードを端末にかざすか、店舗に設置されたQRコード等をスマートフォンで読み取る方法が一般的です。基本的には事前に入金しておく先払い型ですが、アプリによっては後払いに対応しているものもあります。
▼QR決済について詳しく知りたい方は下記からご覧ください。
QRコード決済のメリット・デメリットは?店側とユーザー側の視点で比較!
【利用者】電子マネーのメリット
利用者側から見た場合の電子マネーのメリットを解説します。主なメリットは次の2点です。
楽に決済ができる
電子マネーはタッチ決済やQRコード決済を活用するため、現金に触れることなく支払いを済ませられます。小銭を用意する必要がなく、楽に素早く決済ができるのが大きなメリットです。
ただし、ECサイトで利用する際にはクレジットカード番号等を入力するのが面倒に感じる人もいます。現金に触れずに済むことは、主に実店舗で利用する場合に得られるメリットと捉えてください。
ポイントを貯められる
電子マネーの中には、支払った金額や購入した商品の種類に応じてポイントが付与されるのが一般的です。現金で購入した場合、店舗独自に発行するポイント以外は貯めることができません。
ポイントを貯めていくことで、ポイントを支払い金額に充当できるなどお得に買い物をすることができます。ポイントが貯まることは、電子マネーを利用するメリットといえるでしょう。
【店舗運営者】電子マネーのメリット
次に、店舗運営者から見た場合の電子マネーのメリットについて解説します。店舗運営者にとっての主なメリットは次の2点です。
未回収リスク低減
電子マネーはデータで処理されるため、現金の数え間違いなどによる未収金リスクが発生しません。ECサイトにおいても、払込票などによる後払いでは支払い忘れなどが生じやすいため、電子マネーで未回収を確実に防げる点が大きなメリットです。ECサイトでも顧客がその場で決済できるため、支払いまでのタイムラグが発生しない点がメリットといえるでしょう。
さまざまな顧客に対応できる
冒頭でも触れた通り、電子マネーの利用者は着実に増加しています。電子マネーでの支払いに対応することにより、より幅広い層の顧客に店舗やサービスを利用していただける点がメリットです。
電子マネーによっては、クレジットカードを発行できない年齢の顧客も利用できる場合があります。さまざまな顧客に対応しやすくなることは、電子マネーのメリットといえるでしょう。
【利用者】電子マネーのデメリット
電子マネーを利用するには、最初に申込みや利用者登録を行う必要があります。利用開始時にやや手間がかかることは、電子マネーのデメリットとなり得るでしょう。
また、カードやスマートフォンを紛失したり落としたりした際に、不正利用されることも考えられます。不正利用のリスクをゼロにすることは実質的にできないため、電子マネーの紛失や置き忘れなどには十分に注意しなければなりません。
【店舗運営者】電子マネーのデメリット
電子マネーを決済方法として導入する場合、店舗運営者側にとってもデメリットやリスクとなり得る面があります。具体的には、次の2点に注意が必要です。
チャージバックのリスク
チャージバックとは、電子マネーが不正利用された際に発行者が店舗運営者に対して代金返還を求めたり、支払いを拒否したりすることを指します。店舗運営者がすでに商品を発送していたとしても、代金を回収することができません。回収不能となった代金は損金として処理するしかなく、店舗にとって大きな損失となります。
カゴ落ちリスク
顧客がクレジットカード情報の入力を面倒に感じたり、電子マネーとの連携ができなかったりした場合に、決済完了前に購入を断念することが考えられます。ECサイトにおいては、ショッピングカートに商品が入れられたまま購入に至らない「カゴ落ち」と呼ばれる現象です。決済方法が分かりにくいと顧客が感じることのないよう十分に配慮することで、カゴ落ちリスクを低減させる必要があるでしょう。
▼カゴ落ちやその対策についてより詳しく知りたい方はこちら
電子マネーでの支払いが心配な場合はatone(アトネ)がおすすめ
電子マネーを利用することで多くのメリットを得られる反面、デメリットとなりかねない面も持ち合わせています。デメリットの部分が気になる場合には、後払い決済のatone(アトネ)がおすすめです。atone(アトネ)の特徴や魅力について見ていきましょう。
業界唯一のポイントサービス
atone(アトネ)は後払い決済サービスのため、利用代金は翌月末までにコンビニでまとめて支払います。atone(アトネ)の大きな特徴の1つは、コンビニ後払い決済サービスとして唯一ポイントサービスを提供している点です。
具体的には、atone(アトネ)での決済時に充当できるポイントが支払いごとに0.5%還元されます。ポイントによる支払いを希望する顧客にも対応可能です。
業界最低水準の手数料
atone(アトネ)の決済手数料は2.5%〜と、業界最低水準です。決済手数料を抑えられるため、経費の節約に繋がります。
決済手数料は積み重なると決して小さくない経費の金額となるはずです。業界最低水準の決済手数料で後払い決済を利用できることは、atone(アトネ)のメリットといえるでしょう。
未回収リスクはゼロ
後払いには未回収リスクが付き物です。支払い期限までの期間が長い場合はとくに、顧客が支払いを忘れてしまうリスクは決して低くありません。
atone(アトネ)では、未回収リスクを運営会社であるネットプロテクションズが100%保証します。たとえ顧客からの入金が確認できなかった場合も、手元に売上金が渡らないといった事態を避けられるのです。
カゴ落ちリスクの低減
atone(アトネ)は電話番号とパスワードのみで利用できるため、幅広い顧客が利用できます。顧客の中にはクレジットカードを持ちたくない方や、クレジットカードそのものを持っていないという方もいるはずです。こうした顧客がatone(アトネ)を活用することで、機会損失を最小限に抑えられるでしょう。
カゴ落ちリスクの大きな原因の1つに、決済方法が分かりにくいことが挙げられます。atone(アトネ)は決済方法がシンプルで分かりやすいため、最後までスムーズに買い物を進めやすいでしょう。カゴ落ちリスクを低減できることは、atone(アトネ)をご利用いただく大きなメリットといえます。
電子マネーと後払い決済でより便利な支払いへ
電子マネーはデータでお金をやり取りできる仕組みであり、今後も活用が広がっていくことが予想されます。一方で、電子マネーにはさまざまな種類があり、それぞれ利用シーンが異なるのも事実です。
店舗側としては、できるだけ多くの電子マネーに対応できるようにしておくことで顧客の幅が広がります。電子マネーの不正利用など、リスクの面が不安な場合は後払い決済のatone(アトネ)がおすすめです。電子マネーと後払い決済で、より便利な支払い方法を提供していきましょう。