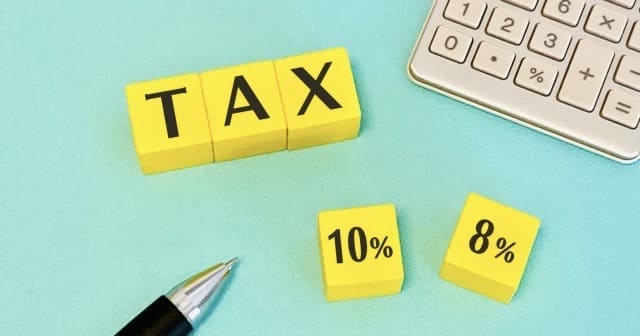ECサイト運営
SKUとは?重要性や注意点をわかりやすく解説
SKUとは、在庫管理において使われる物流用語の一つです。
在庫管理を担当しているとよく目にする言葉ですが、正確な意味について調べたことはないという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、SKUを用いて在庫を管理するメリット・デメリットについて解説します。
また、SKUの設定方法や設定する際の注意点も併せて紹介しますので、ぜひ役立ててください。
目次
SKUとは
SKUはStock Keeping Unitの略で、最小の在庫管理単位を表す言葉です。
もともと物流業界特有の用語でしたが、現在では業界を問わず在庫管理の際に広く使われています。
たとえば、Tシャツを在庫管理する場合、白・黒の2色とS/M/L/LLの4サイズ展開の商品があるとします。「何種類の在庫があるか」という言い方をした場合、色の種類を指しているのかサイズの種類を指しているのかが不明確になりかねません。
そこで、SKUを用いて2色×4サイズ=8SKUと表すことにより、在庫管理上の品目数を明確に表せるのです。
SKUの重要性を解説
それでは、なぜSKUを設定しておく必要があるのでしょうか。
そもそも在庫管理の主な目的は「どの商品がどれだけ売れたか」「どの商品がどれだけ残っているのか」を正確に把握することです。
Tシャツであれば、「白のMサイズは在庫が少なくなっているが、黒のLLサイズは在庫が多く残っている」といったことが起こり得ます。
色とサイズの組み合わせを最小単位と考え、SKU単位で在庫管理を進めるほうが分かりやすく、在庫管理の効率化を図ることができます。
こうしたSKUの考え方は、実店舗での販売時はもちろんのこと、ネット通販においても同様の方法で在庫を管理しているケースがほとんどです。
このように、商品の売上や在庫数を正確に把握する上でSKUは重要な役割を果たしています。
SKUのメリット・デメリットとは
SKUを在庫管理に活用するメリット・デメリットをそれぞれ整理しておきましょう。
メリット
SKUを活用する大きなメリットとして、効率的な在庫管理が実現しやすくなる点が挙げられます。
在庫状況をリアルタイムで把握できるため、特定の色やサイズが品切れになってしまうといったリスクを防げるからです。
また、商品のリニューアルや販促キャンペーンなどを実施する際にも、SKUを活用することで柔軟な対応が可能となります。
新旧アイテムを区別して販売するのであれば、それぞれ別のSKUを適用することで別商品として在庫管理を行うことが可能になるからです。反対に新旧アイテムを区別することなく売り切りたい場合には、新旧アイテムを同一SKUで管理することによって在庫ロスを回避できるでしょう。
デメリット
SKUによる在庫管理方法は一度定着すれば非常に便利ではあるものの、仕組みが定着するまでに時間がかかりがちです。
SKUによる在庫管理のメリットを活かし、仕入れや販売の効率化を実現するまでには一定の時間がかかるでしょう。
また、在庫管理システムの導入・運用コストがかかるのは避けられないため、店舗にとってコストの増加につながります。
小規模店舗にとって、こうしたコストをかけてまでアイテム点数を増やすべきかは悩みどころとなるでしょう。SKUを活用する費用対効果が十分に得られるかどうかは、扱う商品点数や店舗の規模などと照らし合わせて慎重に判断する必要があります。
SKUの設定方法とは
SKUの基本的な設定方法と、個別に検討すべきケースについて解説します。
基本的な設定方法
商品識別コード(JANコード)が付与されている場合には、JANコードを基準にSKUを設定するケースが多く見られます。JANコードとは、一定のルールに従ってメーカーが自由な裁量で発行している識別コードのことです。一般的に、JANコードは「バーコード」で表示されます。色やサイズなどが異なれば別のJANコードが付与されているため、SKUとして割り当てやすいでしょう。
個別で検討すべき場合
JANコードをSKUに割り当てた場合、例外が発生することが考えられます。次のようなケースについては、商品ごとにSKUの割り当て方を個別に検討する必要があるでしょう。
料金が異なるケース
同一の商品でも料金が異なる場合、JANコードをSKUに割り当てるだけでは区別がつきません。このようなケースでは、料金ごとに別々のSKUを割り当てる必要があります。
たとえば、キャンペーン期間中などに一時的に値段を下げて販売したい場合、通常価格で販売する場合とキャンペーン価格で販売する場合とでは別のSKUにしておかなければなりません。同一のSKUにしてしまうと売上・発注管理がしづらくなるため注意が必要です。
内容量が異なるケース
同じ商品でも内容量が異なる場合、内容量に応じて販売価格を変えるケースが多いでしょう。このような場合、内容量ごとに別のSKUとして扱うのが基本となります。
ただし、一時的なキャンペーンなどで増量するようなケースでは、販売価格を変えないのであれば同一のSKUとして扱うこともあり得ます。とくに通販系の在庫管理ではよくある事例のため、SKUを新たに付与するべきか、既存のSKUを使用するべきか慎重に判断する必要があるでしょう。
内容が同じでパッケージのみ異なるケース
商品識別コードが同じ商品をパッケージを変えて販売する場合は、同一のSKUで扱うケースが多く見られます。商品そのものが同じもので、かつ販売価格も同じであれば、あえて別の商品として扱う理由がないからです。
ただし、キャラクターとの限定コラボ企画など、パッケージが商品を訴求する上で重要な要素となっている場合は別のSKUで管理したほうが無難でしょう。コラボ企画によって商品の売上がどの程度伸びたのか、効果を検証する際に必要な資料となるからです。また、ライセンス料や制作費など、通常の商品よりも多くのコストがかかっていることも考えられます。利益を正確に算出するためにも、コラボ企画の場合はSKUを分けて管理するのがおすすめです。
SKUを設定する際に気を付けたいポイントとは
SKUを設定する際に注意しておくべきポイントを紹介します。次の3点を押さえてSKUを割り当てることで、出荷や発注時の事故を防ぎましょう。
1,重複を避ける
1つのSKUに対して1つの品目を登録することは、必ず押さえておくべき大前提と考えてください。異なる商品間でSKUが重複していると、発注や出荷の際に混乱を招く原因となるため十分に注意する必要があります。
将来的に商品点数が増えることも念頭に置き、SKUのつけ方を工夫することが大切です。SKUの桁数は余裕をもって確保し、商品点数が増えても対応できるようにしておきましょう。
2,桁数を合わせる
SKUの桁数が商品やカテゴリごとに異なっていると、商品管理がしにくくなってしまいます。基本的にはJANコードの桁数(13桁)に合わせ、13桁前後に設定するのが無難でしょう。
桁数があまりに多いと、視認性が低下したり在庫管理システムに登録しづらくなったりすることが懸念されます。全ての商品の桁数を合わせることにより、システム上でSKUをソートする際にも扱いやすくなるでしょう。
3,使用する文字に注意する
SKUに英字を使用する場合、大文字・小文字は必ずどちらかに統一してください。在庫管理システムによっては、大文字と小文字を区別して認識しないものもあるからです。たとえば、S/Lの2サイズ展開の商品を大文字と小文字で区別しようとしても、システム上では同じ商品として認識されてしまう恐れがあります。
また、SKUの先頭に数字の「0」を使用するのは避けましょう。表計算ソフトが典型例であるように、先頭の0を省略して表示・認識するシステムも少なくないからです。この場合、「0123」と「123」はどちらもシステム上では「123」と認識されてしまいます。別々のSKUを登録していたはずが、異なる商品間でSKUが重複するといった事故につながりかねないため、先頭に「0」を使用しないよう注意してください。
SKUを活用して自社の在庫管理を効率化しよう
SKUは在庫管理を効率化する上で重要な役割を果たしています。一方で、SKUによる在庫管理にはメリット・デメリットの両面があることを理解しておくことが重要です。
今回紹介したポイントを参考に、ぜひSKUを活用した在庫管理の効率化を推進してください。SKUを効果的に活用することで、いっそう合理的な店舗運営が可能になるでしょう。
EC・デジコン事業者様におすすめの決済サービスのご紹介
ECサイトでの売上を高める有効な取り組みの1つに、決済方法を充実させることが挙げられます。ユーザーのニーズに応じて多様な決済手段を用意しておくことは、LTVの向上やカゴ落ち防止、新規顧客獲得につながるでしょう。
atone(アトネ)は、業界最低水準の手数料で利用できる後払い決済サービスです。業界唯一のポイントシステムによりリピート率アップにも貢献します。
atone(アトネ)の特徴や導入実績について、より詳しくご覧いただける資料をご用意しています。気になる方はぜひ資料をご確認ください。