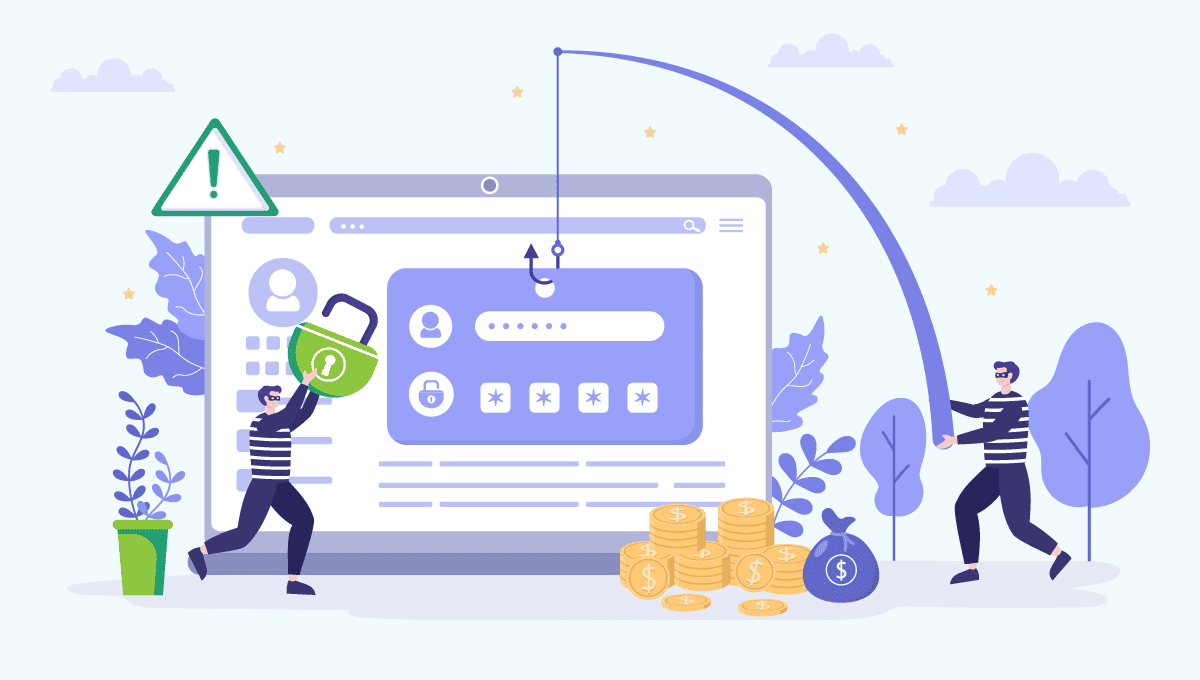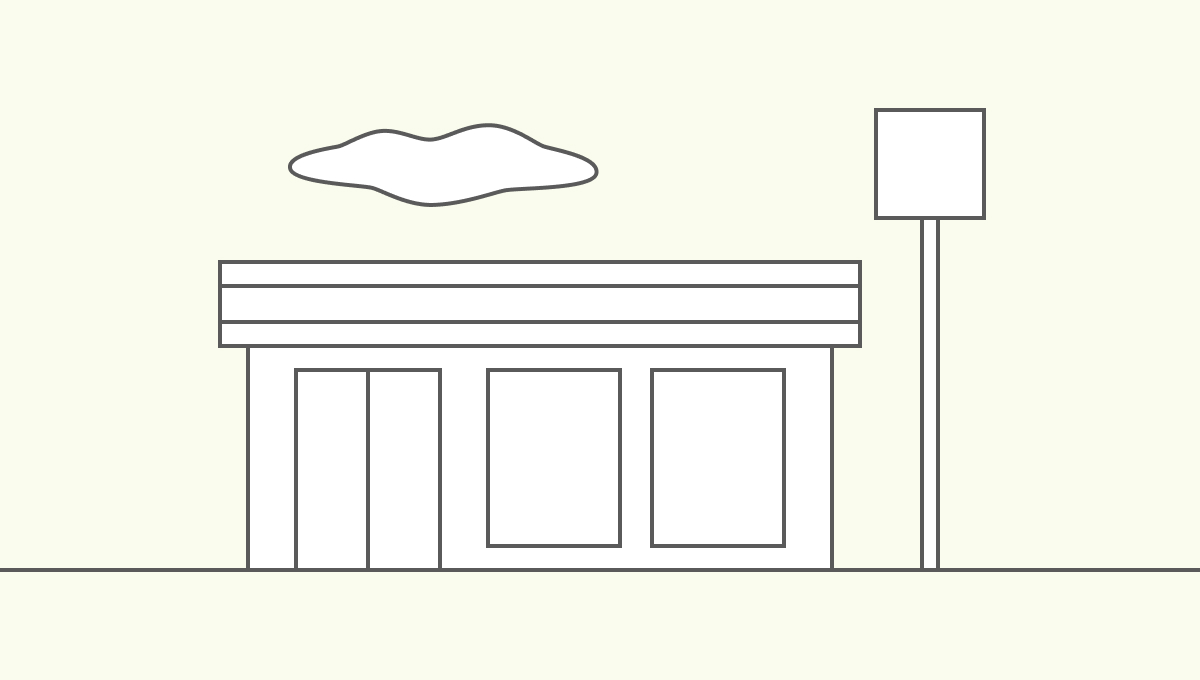決済
【EC事業者向け】代引きの受け取り拒否の原因から対処法、対応策まで解説
EC事業者にとって、商品の受け取り拒否は頭の痛い問題です。とくに代金引換(代引き)の注文者が受け取り拒否をした場合、どう対処するべきか疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。
目次
代金引換・代引きとは?
代金引換・代引きとは、商品の受け取り時に宅配業者が代金回収を代行するサービスです。回収する代金には商品の代金のほか、送料・代引き手数料が含まれます。送料のみ回収する「着払い」との違いに注意が必要です。
多くのECサイトでは、注文時にクレジットカード決済など複数の支払方法を用意しているでしょう。代引きであればクレジットカードを所有していなくてもECサイトを利用できることから、根強いニーズのある決済方法の1つです。
代引き受け取り拒否が行われた場合にEC事業者に発生するリスク
代引きで注文された商品が受け取り拒否となった場合、EC事業者にどのようなリスクが生じるのでしょうか。受け取り拒否に伴う主なリスクについて見ていきます。
コストに関わるリスク
代引き商品の受け取りが拒否された場合、拒否の理由に関わらず返送料はEC事業者側が負担しなくてはなりません。事前に宅配業者の間で割安な送料の契約を結んでいたとしても、返送料は正規価格となるのが一般的です。
また、賞味期限や消費期限時間に関わるリスクのある食品などの場合、受け取り拒否の状態が続くと期限切れになってしまうことも考えられます。商品価値がなくなってしまえば、再販することができないため廃棄せざるを得ません。仕入れコストはそのまま損失となり、EC業者の収益を圧迫する要因となります。
時間に関わるリスク
受け取り拒否が発生すると、商品の返送や再発送のために時間と手間をかけなくてはなりません。宅配業者とのやりとりや注文者への連絡など、本来であれば発生しなかったはずの作業に追われることになるのです。
こうした対応に時間を取られることは、EC事業者にとってリスクとなり得ます。売上や利益につながる他の業務に費やすべき時間が、受け取り拒否への対応に割かれてしまうからです。受け取り拒否の件数が折り重なると、業務時間を圧迫することにもなりかねません。
代引き受け取り拒否が起きる原因
代引き受け取り拒否は、なぜ発生するのでしょうか。さまざまな理由が考えられますが、ここでは代表的な4つの原因を紹介します。
注文者本人が対応していない
よくあるケースとして、配達時に注文した本人が不在で家族など別の人が対応することがあります。商品を注文した事実を家族などが把握していなければ、「注文した覚えはない」と受け取りを拒否する可能性があるのです。
宅配業者としては事実関係を確認する方法がないため、受け取れないと告げられた以上は商品を配送拠点へ持ち帰るしかありません。受け取り拒否として処理され、EC業者に商品が返送されます。
注文者の勘違い
注文者自身が注文したことを忘れていたり、勘違いによって受け取らなかったりするケースが考えられます。間違いなく注文された商品を届けていたとしても「受け取れない」と言われてしまった以上、宅配業者は商品を持ち帰るしかありません。
とくに定期購入商品の場合、注文者の勘違いが発生しやすい傾向があります。注文者としては初回だけ購入したつもりが、2回目以降も届いたために「注文していない商品が届いた」と捉え、受け取りを拒否することがあるのです。
注文者と受取人が異なる
商品が贈り物の場合、受取人に詳細を知らせずに注文していることがあります。知人や家族の氏名が送り主欄に記載されていれば、受け取ってもらえるケースが多いはずです。しかし、送り主がEC事業者名だった場合、受取人は身に覚えのない商品が届いたと考える可能性があります。
また、配送先が法人の場合、商品が注文された経緯を全ての従業員が把握していないことも考えられます。たとえば、総務部が一括注文した商品が届いたものの、他部署の担当者は何がいつ届くのか知らされていなかったようなケースです。誤送や発注ミスを疑い、荷物を受け取らずに引き取ってもらうよう宅配業者に依頼することもあり得るでしょう。
注文者の都合による受け取り拒否
悪質なケースとして、注文者の一方的な都合によって受け取りを拒否することがあります。たとえば、「注文後に必要ないと気づいた」「他店で購入したので不要」といった理由による受け取り拒否などが該当します。
本来なら、注文者自身でキャンセル手続きをしなくてはならないはずです。しかし、注文者側は「支払い前なので不要な商品は断ればよい」と捉えていることもあり得ます。注文者は自分の側に非はないと考えており、EC事業者の対応によってはトラブルに発展することもめずらしくありません。
代引き受け取り拒否された場合の対応方法
もし代引き受け取り拒否されたとしたら、EC業者はどのように対応すればよいのでしょうか。具体的な対応方法について解説します。
出品者側の手配にミスがないか確認する
宅配業者から受け取り拒否が発生していると連絡を受けたら、まずは出品者側に発送手配ミスがなかったか確認しましょう。住所の入力間違いなど出品者側のミスであれば、EC事業者が返送料を負担するしかありません。
購入者と連絡を取る
間違いなく注文通りに発送していることが確認できたら、すみやかに購入者と連絡を取りましょう。購入者の勘違いや同居者の受け取り拒否などの行き違いがあった場合、購入者に確認が取れた時点で商品を再送すると伝えます。この時、出品者と購入者のどちらが返送料・再送料を負担するのかを明確にしておくことが大切です。
購入者が意図的に受け取り拒否していた場合、トラブルに発展する可能性があります。たとえば購入者が受け取り拒否によってキャンセルできたと認識しているようなら、キャンセル処理が完了していないことを説明し、了承してもらわなくてはなりません。
もし購入者に受け取る意思がないようなら、返品処理を行う必要があります。返品処理に伴い送料や代引手数料が発生することを伝え、支払期限を提示しましょう。
ショップの規約に従って対応する
購入者の意思確認をしたら、ショップの規約に従って対応していきます。返送料や代引き手数料に関する規約を提示し、請求メールを送りましょう。
▼受け取り拒否に対する請求メールの例文
〇〇様
このたびは当ショップをご利用いただき、誠にありがとうございます。
【ショップ名】の〇〇と申します。
先日ご注文いただきました商品を発送いたしましたが、お受け取りいただけなかったため商品が当ショップへ返送されてまいりました。
当ショップでは発送後のキャンセルは承っておりませんので、規約にもとづき送料・返送料・代引き手数料をご負担いただきたく存じます。
つきましては、下記の代金を請求させていただきますので、お支払い期限までにお振込をお願いいたします。
注文番号:〇〇〇〇
注文日時:〇〇年〇月〇日
ご注文者:〇〇様
支払方法:代金引換
商品名:〇〇
送料:〇〇円(税込)
返送料:〇〇円(税込)
代引き手数料:〇〇円(税込)
合計金額:〇〇円(税込)
お支払い口座:〇〇銀行〇〇支店 普通〇〇〇〇〇〇〇〇〇
お支払い期日:〇〇年〇月〇日
支払いに応じてもらえない場合や悪質な受け取り拒否の場合は、法的措置も含めて検討する必要があります。EC事業者が取り得る法的措置は次の通りです。
▼法的措置の例
- 内容証明郵便の送付
- 簡易裁判所への支払督促の申立
- 警察へ被害届を提出
ただし、法的措置を講じるには少なからず時間や費用がかかります。可能な限り購入者に納得してもらい、支払いに応じてもらうのが理想です。
受け取り拒否発生時のお客様への確認事項
お客様とのトラブルに発展するのを防ぐには、受け取り拒否が発生した際の初動対応が非常に重要です。お客様に連絡を取る際は、次の事項を必ず確認しましょう。
- 受け取り拒否の理由(お客様都合かどうかがポイント)
- 商品を受け取る意思があるか
- 返送料や代引き手数料の支払いに応じてもらえるか
電話でお客様に連絡を取った場合、確認した事項をメールでも送付しておくことで記録が残ります。お客様が感情的になっていることも想定されるので、EC事業者側は手順に従って冷静に対応することが大切です。
受け取り拒否の事前対策
受け取り拒否ができる限り発生しないよう、事前対策を講じておくことも大切です。受け取り拒否の防止策として、EC事業者が講じておきたい対策を紹介します。
発送後のキャンセルができない旨を規約に明記する
ショップの規約には、発送後にキャンセルできない旨を必ず明記しましょう。キャンセルに関する規約があれば、注文者に対応する際に根拠として示すことができます。
キャンセルが可能なタイミングについてはトラブルの原因になりやすいため、注文受付時や商品発送時のメールにも記載しておくことをおすすめします。複数箇所に記載しておくことで、規約を見落としていたのは注文者側の過失であることを理解してもらいやすくなるはずです。
受け取りを拒否した際の対応を規約に明記する
代引き商品を受け取り拒否した場合の対応について、規約に明記しておきましょう。注文者が負担するべき範囲を明確にすることで、全ての注文者が公平な条件で取引していることを示す根拠となります。
▼受け取りを拒否した際の規約例
商品発送後にキャンセルした場合、以下の代金をご負担いただきます。
- 返送料
- 代引き手数料
- 梱包資材料
悪質な注文者の履歴を記録しておく
受け取り拒否が度重なった注文者や、悪質な受け取り拒否が見られた注文者を履歴に残しておくことも大切です。同じ人物から再び注文が入った場合、過去の履歴を元に注文拒否などの措置を講じることができます。
悪質な注文者はショップ側でブロックをかけてしまい、注文できない状態にするのも1つの方法です。悪質な注文者を排除することで、EC事業者は本来の業務に集中しやすくなります。結果的に優良顧客へのサービス品質が向上し、ショップの評判を高めることにも繋がるはずです。
まとめ
代引きの受け取り拒否は、EC事業者にとって利益を圧迫する直接的な原因となります。受け取り拒否が発生した際の対応を決めておき、手順通りに対応していくことが大切です。
また、そもそも受け取り拒否が発生しにくい仕組みを作っておくことも重要なポイントといえます。キャンセルが可能なタイミングを注文者に周知する仕組みを整え、受け取り拒否を未然に防ぎましょう。
他にも、決済手法を充実させることも有効な手段です。例えば、後払い決済サービスatone(アトネ)は代金の未回収リスクを100%保証しているので、安心して導入いただけます。さらに、自社で催促状を発行・送付する手間を削減できるため、請求業務の効率化にもつながるでしょう。受取拒否などによる未回収リスクが発生するのが不安な事業者様は、ぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。