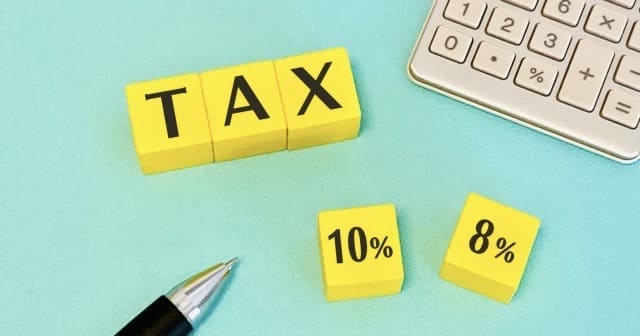ECサイト運営
すぐにわかる!ランニングコストの意味とは?イニシャルコストとの違いも
日頃、暮らしや仕事の中で「ランニングコスト」という言葉を耳にすることがあります。何となく使っていた言葉ではあるものの、正確な意味を調べたことがない方も多いのではないでしょうか?
目次
ランニングコストの意味とは?
ランニングコスト(runnnig cost)は、日本語では「維持費用」などと訳されます。runnnigには「走ること」のほかに「運営」という意味があることから、runnning costは運営にかかる費用という意味を表しているのです。
私たちが暮らしていく中で、何かを維持するために費用がかかることがあります。たとえば住宅では日常的に電気や水道を使うため、電気代や水道代がかかっているはずです。こうした費用は一度支払えばずっとサービスを利用し続けられるわけではなく、使った分だけ費用を負担しなくてはなりません。
このように、何かを使い続けていく上で支払い続ける必要のある費用をランニングコストと呼んでいるのです。
【状況別】ランニングコストの例を紹介
では、具体的にどのような費用がランニングコストに含まれるのでしょうか。ビジネスと日常生活のそれぞれのシーンに分けて、ランニングコストの例を見ていきましょう。
ビジネスにおけるランニングコストの例
ビジネスにおけるランニングコストには、たとえば次のようなものがあります。
人件費
従業員に月々支払う給与は、継続的に発生する費用の1つです。雇用契約が続く限り発生する費用であることから、ランニングコストといえます。
水道光熱費
事務所や店舗で使用する照明や空調には電気代がかかっています。また、手洗いや皿洗い、トイレで水を使えば水道代の支払いも必要です。月々の水道光熱費は事務所や店舗を使い続ける限り支払いが発生するため、ランニングコストに含まれます。
家賃
事務所や店舗の家賃も典型的なランニングコストです。賃貸物件を契約している期間中は月々支払う必要があることから、事業を維持する上で必要な費用といえます。
日常生活におけるランニングコストの例
ランニングコストは、私たちの日常生活でも発生しています。たとえば次に挙げる費用は、いずれも維持するため・使い続けるために必要な費用といえるでしょう。
水道光熱費
住宅で使用する照明や冷暖房器具をはじめ、さまざまな家電製品を使うには電気が必要です。また、風呂やトイレ、洗面所では毎日水を使っています。電気や水を使い続けるために必要な水道光熱費はランニングコストの一種です。
家賃
住宅の契約を維持するために必要な家賃もランニングコストに含まれます。賃貸物件に住み続けている限り、毎月必ずかかる費用だからです。
通信費
インターネット回線使用料やスマートフォンの月額利用料などの通信費は、使い続けるために支払う必要のある費用といえます。月額固定料金制の場合も従量料金制の場合も、何らかの費用が毎月発生するという意味でランニングコストに含まれます。
消耗品購入費
蛍光灯や電球、洗剤・掃除用品、ティッシュペーパーといった消耗品は、定期的に購入する必要があります。暮らしを維持するために欠かせないものですので、いずれもランニングコストに含まれる費用です。
食費
私たちが生きていくには食べ物を摂らなくてはなりません。飲食物にかかる費用も、暮らしを維持する上で必要なランニングコストといえます。
ランニングコストに関する疑問
ランニングコストについて、よくある疑問と解説をまとめました。混同しやすい「イニシャルコスト」「ライフサイクルコスト」「固定費」などとの違いについても解説していますので、理解を深める上で役立ててください。
イニシャルコストとの違いは?
イニシャルコスト(initial cost)とは「初期費用」「導入費用」のことです。事業を始める際にかかる費用や新たに機器などを導入する際にかかる費用を指します。つまり、「導入時に一度だけかかる費用」と捉えてください。
たとえば新たにプリンターを導入する場合、プリンター本体の購入費用がイニシャルコストです。これに対して、インクが切れるたびにかかるインクカートリッジ代がランニングコストに相当します。
飲食店を開業する場合であれば、開業時にかかる物件取得費や内装費、調理器具などを購入するための費用がイニシャルコストです。開業後、店舗を維持するために必要な家賃や水道光熱費などはランニングコストにあたります。
イニシャルコストを抑えることができたとしても、その後のランニングコストによっては費用がかさむ原因となります。反対に、ランニングコストが安くてもイニシャルコストが高すぎると導入時の負担が大きくなってしまうのです。
▼イニシャルコストとの違いや算定方法についてより詳しく知りたい方はこちら
ランニングコストとイニシャルコストの違いとは?実例、算定方法を解説
ライフサイクルコストとの違いは?
ライフサイクルコスト(life cycle cost)は「生涯費用」と訳されます。製品や構造物(建物や橋、道路など)が作られてから、その役割を終えるまでにかかる費用をトータルで捉えたものです。
たとえば、プリンターを購入してから故障して買い換えるまでの期間にかかった総額が、このプリンターのライフサイクルコストにあたります。プリンターを使い続けていた間にかかったインクカートリッジ代や電気代もライフサイクルコストの一部です。
つまり、ライフサイクルコストは「イニシャルコスト+ランニングコスト」で構成されています。イニシャルコストが多少高くても、ランニングコストを節約できる製品や耐久性が高い製品であれば十分な費用対効果が得られるでしょう。反対にイニシャルコストが安い製品でも、頻繁に修理費がかかるようではライフサイクルコストがかさんでしまいます。
導入費用だけ・維持費用だけを見て費用対効果を判断するのではなく、その製品や構造物の耐用年数を元にライフサイクルコストを試算しておくことが大切です。
固定費との違いは?
固定費とは、売上の増減に関わらず発生する費用のことです。店舗を運営するケースであれば、店舗の家賃は毎月必ずかかることから固定費に分類されます。
一方、店舗を維持するためには家賃さえ支払っていればよいわけではありません。店舗に設置された照明器具の蛍光灯や電球が切れて交換することもあるでしょう。皿やグラスが割れてしまい、買い換えが必要になることもあるはずです。こうした消耗品にかかる費用は「変動費」と呼ばれます。店舗を維持するために必要な固定費と変動費を合わせたものがランニングコストです。
このように、固定費はランニングコストに含まれています。ランニングコストを試算する際には、固定費と変動費に分けて考えましょう。固定費はランニングコストの中でも常にかかる費用のため、できるだけ固定費を抑えたほうが望ましいとされています。店舗運営であれば家賃が高すぎると収益を圧迫する原因になりやすいことから、できるだけ家賃の安い物件を探すことが大切です。
ランニングコストを略すとなんという?
ランニングコストはrunning costの頭文字を取って「RC」と呼ばれることがあります。費用に関してRCという言葉を見かけたら、ランニングコストを指していると捉えてください。
これに対して、イニシャルコスト(initial cost)の頭文字を取って「IC」と表すこともあります。RCとICの関係は下記の通りです。
- IC=initial cost(初期費用・導入費用)
- RC=runnning cost(維持費用)
- ライフサイクルコスト=IC+RC
まとめ
ランニングコストは「維持費用」のことであり、何かを使い続けていくために必要な費用を指します。対義語はイニシャルコスト(初期費用・導入費用)です。ビジネスだけでなく、日常生活においてもさまざまなランニングコストが発生しています。新たに機器などを導入する際には、イニシャルコストとランニングコストの両面から費用を考えることが大切です。
集客にかかるランニングコストを抑えるためには、決済方法を増やす施策を考えてみてはいかがでしょうか。後払い決済を導入する場合、atone(アトネ)がおすすめです。atone(アトネ)の決済手数料は業界最低水準で導入も簡単にできるため、ランニングコストだけでなくイニシャルコストも抑えつつ、利益向上を目指すことができます。
atone(アトネ)についてより詳しく知りたい方は、ぜひ資料をダウンロードしてみてください。